新卒3年で辞めるのは早い ?割合や理由、辞めたいときの対処法を解説
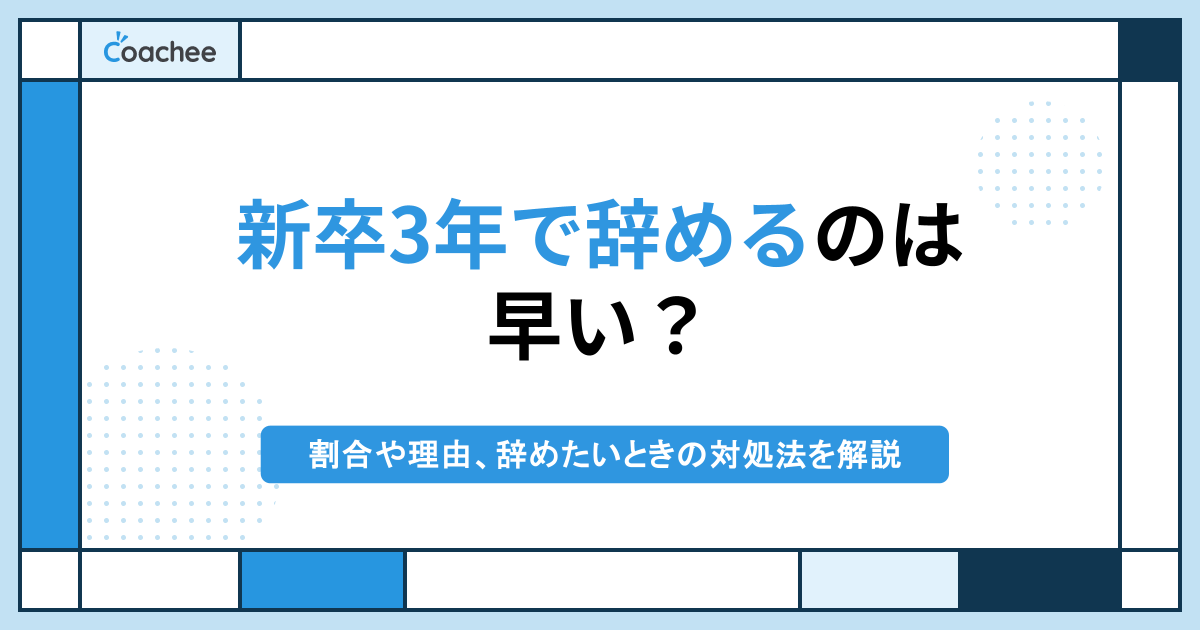
「新卒3年以内の退職は不利になるのでは?」
「同期が次々と辞めていく中、このまま続けるべきか迷っている」
新卒入社から3年以内での退職を考えながらも、さまざまな不安や悩みを抱えている方は多いでしょう。しかし、3年以内に退職する人は約3割いるなど、珍しい選択ではありません。
本記事では、3年以内の退職にまつわるリスクや対処法、転職を成功させるためのポイントを具体的に解説します。新卒での退職を考えている方にとって役立つ内容です。
新卒3年目で辞めるべきか悩んでいる方には、キャリア相談プラットフォームのcoachee(コーチー)の利用をおすすめします。
サイト内から自分が属している業界のコーチを選べるため、目的に合わせて相談することが可能です。「転職をするべきかどうか」「スキルを活かした転職方法」なども相談できるため、今後のキャリアチェンジにも役立つでしょう。
1回1,000円~利用できるため、まずはサービス内容をチェックしてみてください。
新卒3年で辞めるのは早い?不利になる?離職率の割合を解説
新卒入社から3年以内の退職は、必ずしも早くなく、転職活動で不利になるわけではありません。応募先企業は勤続年数だけでなく、在職中に獲得したスキルや実績、将来性を重視して採用を判断するためです。
実際に多くの企業が第二新卒枠や未経験者向けの求人を設けており、応募者の可能性に注目しています。面接では経験を通じて身につけた知識や、入社後に達成したい目標などをアピールできれば、転職のチャンスがあるでしょう。
3年以内に辞める割合
厚生労働省の調査によると、新卒入社後3年以内の離職率は新規高卒就職者で38.4%、新規大卒就職者で34.9%に達しています。つまり、3人に1人が早期に退職しています。
また、マイナビ転職が実施した調査によると、退職のタイミングは、1年目が17.7%、2年目が23.0%、3年目が25.7%と、年数を重ねるごとに退職者が増加する傾向です。中でも3年目での退職が最も多く、3年以内に退職した人の合計は全体の66.4%にも上ります。
1年目は新しい環境に適応しようと努力する一方で、2年目以降は仕事への理解が深まるにつれて目指したいキャリアを考え始める社会人が増えていくことがわかります。
出典:新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します|厚生労働省
出典:とりあえず3年働いてから転職するべき? 辞める・辞めないリスクと対処法|マイナビ転職
「とりあえず3年働く」は正しい?
「とりあえず3年は働いたほうがいい」という考えには、明確な根拠がありません。単に長年続いてきた価値観から、同じ職場で3年程度働けば余裕も生まれ、やりがいを見出せるだろうなどという考えによるものです。
企業側も早期離職者を減らしたいという思惑から「3年は働いてほしい」という考えを持っています。ただし実際には、個人の状況や目標によって最適な在職期間は異なるため、一概に3年働くべきとは言えないでしょう。
新卒を3年で辞める理由!知恵袋の口コミも解説
本項では、新卒を3年で辞める理由をYahoo!知恵袋の口コミも交えながら詳しく解説します。
- 収入アップを目指したいから
- やりがいのある仕事をしたいから
- 新しいスキルを身につけたいから
自身が抱える退職したい理由と同じ箇所はあるのかどうかを確認しておきましょう。
1.収入アップを目指したいから
新卒3年目、転職を考えています。
新卒で中堅のIT企業に就職しました。
給料が安く、残業代もボーナスも出ないため、転職を考えています。
引用:ヤフー知恵袋
上記のように、給与面での不満から、3年以内の転職を考える若手社会人は多い傾向です。現在よりも高い収入を確保したい、将来の昇給に不安を感じるなどの理由が挙げられます。
特に先輩社員の昇進ペースを目の当たりにすると、自分の思い描く収入が見込めないと判断し、早期の転職を選択することがあります。
2.やりがいのある仕事をしたいから
やりたい仕事が見つかり、前の職場では実現不可能な環境だった
引用:ヤフー知恵袋
上記の口コミのように、やりたいことができる仕事がしたいという理由から新卒3年で辞める人も多い傾向です。
また「モチベーションを向上できる業務に携わりたい」「興味のある仕事をしたい」などの場合、転職で仕事内容を変えたいケースがあります。「入社後に希望の部署に配属されなかった」「2年で部署異動になった」など、やむを得ない理由で仕事にやりがいが感じられない、興味が持てないなどの理由も挙げられます。
3.新しいスキルを身につけたいから
現在中小企業で営業をしている新卒3年目の25歳の者です。
現在、経理や総務等バックオフィスにキャリアチェンジをしたいと考え、転職活動を行っています。
引用:ヤフー知恵袋
3年以内の転職を考える理由として、新たな経験やスキルを得たいという意欲が挙げられます。職場によっては業務がルーティンワーク化してしまい、スキルアップに取り組みづらい環境も存在します。
別の職場でキャリアアップを目指すために、早期の転職を選択する若手社会人も増加傾向です。
新卒3年以内に辞める4つのリスク!不利になる?
新卒入社から3年以内での退職には、以下のようなリスクがともないます。
- 仕事のスキルや社会人経験が身についていない
- 「すぐに辞める」と思われる場合もある
- 人間関係を最初から作る必要がある
- 福利厚生を十分に受けられない
転職活動や次の職場で直面する可能性がある課題は、具体的な対策とともに解説していきましょう。
1.仕事のスキルや社会人経験が身についていない
3年以内の退職では、応募先企業が求めるスキルや実績が不足し、選考で苦戦する可能性があります。特に即戦力採用では、業界知識や専門的なスキルの習得が重視されるため、十分な経験を積めていないと不利になりがちです。
したがって経験がない場合は、第二新卒枠での応募も視野に入れましょう。また、転職では一般的なビジネスマナーの習得が前提となるため、在職中からしっかりと基礎的なマナーを身につけておく必要があります。
2.「すぐに辞める」と思われる場合もある
短い勤続年数は「また同じように短期間で退職するのでは」「仕事への意欲が低いのでは」などの懸念を企業側に抱かせる可能性があります。そのため面接では、仕事経験を通じて明確になった志望動機や長期的なキャリアビジョンを具体的に説明できるよう準備しましょう。
例えば「営業職を経験し、より専門的な企画職に挑戦したい」など、前向きな理由とともに今後の展望を伝えられるとよいでしょう。
3.人間関係を最初から作る必要がある
転職先では人間関係を一から構築する必要があります。新卒入社と異なり、気軽に相談できる同期がいない環境で、新たな人間関係作りに苦労する可能性もあるでしょう。
この状況を改善するには、社内イベントなどへの参加が有効です。先輩社員に業務の相談をしたり、ランチに誘ったりするなど、自分から積極的に人間関係を広げましょう。
4.福利厚生を十分に受けられない
福利厚生は一般的に勤続年数が長いほど充実します。3年以内の退職では、住宅手当や退職金など、長期勤続を前提とした制度の恩恵を受けにくいのが現状です。
実際に退職金は勤続年数や給与額によって計算されるため、3年以内の退職では支給額が少なくなったり、支給対象外となったりするケースが多い傾向です。
新卒でとりあえず3年働いてから辞める4つのリスク
本項では、新卒でとりあえず3年働いてから辞める4つのリスクを解説します。
- ストレスが溜まる
- ポテンシャルを評価される第二新卒でなくなる
- 辞めづらくなる可能性がある
- やりたいことに使える時間がなくなる
以下の項で詳しく解説します。
1.ストレスが溜まる
仕事が合わないと感じながら働き続けると、やる気やモチベーションの低下を招き、本来のパフォーマンスを発揮できなくなります。例えば、営業職で成果が出ない状況が続くと、徐々に自信を失い、さらなる成績不振につながる可能性があるでしょう。
人間関係などのストレスで心身の不調が出始めた場合には、休養を取ったり転職を検討したりと、早めの対策が望ましいでしょう。無理に3年間我慢する必要はありません。
2.ポテンシャルを評価される第二新卒でなくなる
第二新卒は、新卒入社から3年以内のビジネスパーソンを指します。4年制大学卒業後なら25~26歳前後が該当し、他社の企業文化に染まっておらず、吸収が早く意欲的な人材として注目されます。
しかし3年以上働いてから転職活動を始めると、第二新卒枠での応募が難しくなる傾向です。経験よりもポテンシャルを重視されやすく、未経験分野へのチャレンジもしやすい第二新卒の間に転職活動するのがおすすめです。
3.辞めづらくなる可能性がある
長期間働くほど、責任の重い仕事や長期的なプロジェクトを任されるようになります。例えば、重要な取引先との窓口担当や、半年以上の開発案件のリーダーなど、簡単には引き継ぎできない立場になると、退職のタイミングを図りづらくなるでしょう。
また、やりがいを感じられないまま働き続けると、仕事自体へのネガティブなイメージが定着し、転職活動にも前向きになれなくなる可能性があります。
4.やりたいことに使える時間がなくなる
「プログラミングのスキルを磨きたい」「別の業界で働きたい」など、目標が明確な場合には辞めないと、やりたいことに使える時間が少なくなります。
もちろん、新卒入社後はさまざまな経験を通じて仕事に慣れる期間も必要です。しかし、別の分野に興味がある場合は、3年にこだわらず転職活動を始めることを推奨します。
新卒3年目で辞めたいと思ったときの4つの対処法
新卒3年目で辞めたいと思ったときは、下記の対策を取ってください。
- 心身の調子を崩す可能性があるときは無理せずに辞める
- やりたいことが明確にあるかを考える
- 辞めることで問題が解決できるかを考える
- 周りの人に相談する
以下の項で、新卒3年目で辞めたいと思ったときの4つの対処法を解説します。
1.心身の調子を崩す可能性があるときは無理せずに辞める
長時間労働やサービス残業を強いられるなど、いわゆる「ブラック企業」的な環境で働く場合には、勤続年数にとらわれず退職を考えましょう。例えば「毎日終電まで働かされる」「休日出勤が当たり前」などの状況では、心身の調子を崩す恐れがあります。
先輩や上司から「誰もが経験している」と言われても、体調不良の兆候が出始めているなら、我慢せずに辞めることを検討してください。
2.やりたいことが明確にあるかを考える
目指す職種や身につけたいスキルが明確な場合には、3年の期間にこだわる必要はありません。特に未経験職種への転職は、若いほうが有利に働くためです。
例えば、現在の一般事務職からITエンジニアを目指す場合や、営業職からデザイナーへの転身を考えている場合など、現職では獲得できないスキルを必要とする転職では、早めの行動が望ましいでしょう。
3.辞めることで問題が解決できるかを考える
退職は必ずしもすべての問題を解決する手段ではありません。なぜなら、転職には相応の時間や労力がかかり、理想的な環境を得られる保証もないからです。
むしろ部署異動や業務変更で状況が改善する可能性もあります。さらに副業してやりたい仕事に挑戦できる環境なら、現職を続けながら新たなキャリアを模索することも可能です。
4.周りの人に相談する
漠然とした退職願望だけで転職すると、次の職場でも同じような状況に陥る可能性があります。そのため、転職経験者など、客観的な意見をくれる相手に相談しましょう。加えて、誰かに話すだけでも思考が整理され、気持ちが落ち着き課題解決のヒントが見つかることもあるでしょう。
身近に相談できる人がいない場合は、キャリアコーチから意見をもらうことをおすすめします。coachee(コーチー)なら、さまざまな業界の専門コーチから現職の悩み相談に乗ってもらえるため、新卒3年で辞める際のアドバイスを受けられます。
無料で登録できコーチ選びも簡単なため、まずは気軽に利用してみてください。
新卒3年以内に辞めるときに転職を成功させるポイント
3年以内での転職を成功させるには、転職活動の面接などでの自己アピールが必要です。そこで、新卒3年以内に辞めるときに転職を成功させるポイントを紹介します。
- ネガティブな退職理由を伝えない
- スキル・実績を明確にして将来のビジョンを伝える
以下の項で詳しく解説します。
1.ネガティブな退職理由を伝えない
転職面接では、前向きな志望動機を伝えることが重要です。一般的に社会人1~3年目の退職理由には「残業が多い」「給与が低い」などが挙げられますが、本音を伝えると次の職場でも同じ理由で辞めるのではと懸念を抱かれがちです。
そのため「営業経験を通じてマーケティングの重要性を実感し、専門的に携わりたいと考えました」など、仕事経験から見出した将来のビジョンを軸に説明するとよいでしょう。
2.スキル・実績を明確にして将来のビジョンを伝える
短期間での退職であっても、培ったスキルや実績を具体的に伝えましょう。具体的には「営業成績で目標比120%を達成」のような数字で表せる実績はもちろん「新規顧客開拓のために展示会を企画・運営」などの経験も、上手にアピールできます。
あわせて「5年後にはチームリーダーとして後輩の育成に携わりたい」「10年後には海外市場の開拓を任される存在に」など、具体的な将来像も示せると良いでしょう。キャリアビジョンが明確な人材は、成長意欲も高く評価されます。
こちらの記事を参考に退職前にしっかり自分について見つめ直してみましょう。
【内定者が選んだ】自己分析ツールおすすめ24選 | 簡単な適性診断サイト,アプリ(全て無料)
新卒3年以内で辞めたいと思ったらcoachee(コーチー)へ相談を
新卒入社から3年以内に退職を考えている人は少なくありません。しかし、早期退職には「仕事のスキルが身についていない」「すぐ辞める人だと思われるかも」などの不安もつきものです。
とはいえ「同期が次々辞める中、自分も迷っている」など、一人で悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
そのようなときは、キャリアの悩み相談に乗ってくれるcoacheeを利用してみてください。
経験豊富なキャリアコーチが、あなたの状況をヒアリングし、具体的なアドバイスをしてくれます。3年以内の退職を考えるきっかけとなった悩みや、転職への不安など、どのような内容でも相談できます。
1回1,000円〜と気軽に利用できる金額なので、一人で抱え込まず、ぜひ専門家に相談して、納得のいく選択につなげましょう。


