【簡単】退職届・退職願の例文・テンプレート!縦書き・横書きの書き方も解説
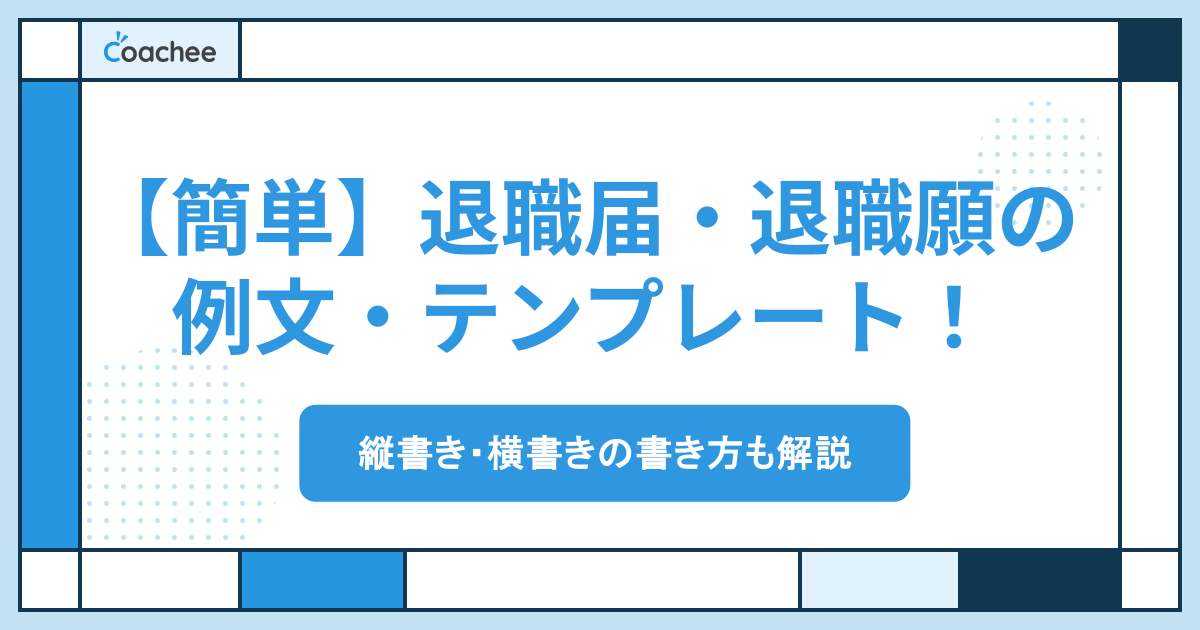
「退職届・退職願の書き方がわからない」
「退職届・退職願の例文やテンプレートが欲しい」
「退職理由をどのように書けばいいか悩んでいる」
このように悩んでいませんか?
本記事では、退職届と退職願の違いから、例文・テンプレート、書き方のポイントまで詳しく解説します。手書きとパソコン作成の違いや封筒の準備、提出方法なども紹介するので、円満退社を目指す方に役立つ内容です。
本記事を読んで、退職手続きをスムーズに進め、次のキャリアへと進みましょう。
「退職の悩みを誰かに相談したい」という方には、キャリア相談プラットフォーム「coachee(コーチー)」がおすすめです。経験豊富なキャリアコーチに相談することで、退職の不安や今後のキャリアプランについて客観的なアドバイスを受けられます。
以下のサイトからサービスの概要をチェックできるため、ぜひご覧ください。
退職届・退職願とは
退職届は会社に退職の可否を問わず、自分の退職を通告する文書です。一方、退職願は、退職を願い出る書類を指します。
退職を意思表示する際に必要な書類について、下記の特徴や違いを理解しておくと役立ちます。
- 辞表との違い
- 必要な理由
- 書き始める前に就業規則を確認する
正しい知識を持って退職手続きを円滑に進められるよう、それぞれのポイントを詳しく解説します。
辞表との違い
会社役員や公務員が提出するのは辞表であり、一般の会社員が提出するのは退職届や退職願です。
役職や所属する組織によって適切な書類が異なるため、自分の立場に合った文書を選びましょう。
必要な理由
退職届・退職願を提出しておくと、自分の意思で退職したことを記録に残せるため、後々「解雇された」と誤解される心配がなくなります。特に失業保険の手続きでは、自己都合退職であることを証明する証拠となるため、給付金の受給開始がスムーズに進むでしょう。
さらに、退職の意思を明確に伝え、退職日や引継ぎなどを調整するきっかけにもなります。会社側も退職の意向を正式に把握できるため、後任の採用や業務の引継ぎ計画を立てやすくなるという利点があります。
書き始める前に就業規則を確認する
退職届・退職願を作成する前に、会社の就業規則を確認してください。
退職の手続きや必要書類、提出期限などが就業規則に定められている場合が多いためです。会社によっては退職届・退職願の様式が指定されている場合もあります。
就業規則に沿って手続きを進めると、スムーズに退職できるでしょう。
退職届・退職願の例文・テンプレート
本項では、退職届や退職願の例文、テンプレートを紹介します。
各テンプレートはワード形式でダウンロードでき、必要に応じて編集可能です。ご自身の状況に合わせてカスタマイズしてご利用ください。
【退職届】縦書き・横書きのテンプレート
退職届のテンプレートには、必要事項が記入しやすいよう整えられた縦書きと横書きの両形式が用意されています。
退職届のテンプレートには「退職届」のタイトル、提出日、所属部署、氏名欄、宛名、本文(退職理由と退職予定日を含む)などの基本要素が含まれています。
以下のリンクから退職届のテンプレートがダウンロードできるので、ぜひ利用してみてください。
退職届のテンプレートはこちら
【退職願】縦書き・横書きのテンプレート
退職願のテンプレートも、縦書きと横書きの両方を用意しており、すぐに活用できる形式になっています。
退職願のテンプレートには「退職願」というタイトルに加え、提出日、所属部署、氏名欄、宛名、そして「一身上の都合により退職いたしたくお願い申し上げます」といった願いの形の本文が含まれています。退職を希望する日付も明記できるようになっています。
以下のリンクから退職願のテンプレートがダウンロードできるため、ぜひ利用してみてください。
退職願のテンプレートはこちら
【例文付き】退職届・退職願の書き方8つのポイント
退職届や退職願を作成する際は、書式やマナーを守る必要があります。
以下の項で詳しく解説します。
1.タイトル
書類の上部中央に「退職願」または「退職届」の見出しを明記します。
大きめに記載するのが一般的で、書類の種類を一目で判別できるようにします。
2.書き出し
本文一行目の下部に「私儀(わたくしぎ)」もしくは「私事」と記載します。
これは「わたくしごとではありますが……」という意味を持ち、謙遜の意を表す言葉です。
3.退職理由
自己都合退職の場合は、一般的に「一身上の都合」と記載します。
ただし、会社都合退職の場合でも会社から退職届の提出を求められるケースがあります。その場合「一身上の都合」とせず「部門縮小のため」「退職勧奨にともない」など退職の理由を明記しましょう。
実態と異なる理由を書くと失業保険の給付期間に影響が出たり、トラブル時に不利になったりするため、退職理由を明確に記載してください。
4.退職日
退職届には上司と合意した年月日を、退職願には退職を希望する年月日を明記します。
年の表記は西暦・元号どちらも使用可能ですが、会社に規定があれば従いましょう。横書きの場合は算用数字で記載してください。
5.文末
退職届と退職願では文末の表現が異なります。
退職届は退職が承諾された後の報告なので「退職いたします」と宣言する形で終わります。一方、退職願は打診の性質を持つため「退職いたしたく~お願い申し上げます」と願う形で締めくくりましょう。
6.届出日
実際に書類を提出する年月日を記入します。
この日付が正式に意思表示した日となるため、「日付は西暦または元号で○○年○月○日と記載します」など、正確に記載する必要があります。
7.部署名、氏名、捺印
行の下方に所属部署と氏名を記載します。
所属は正式な部署名、名前はフルネームで記載し、末尾に印鑑を押します。この際、シャチハタは避け、認印を使用するのがマナーです。
8.宛名
組織の最高執行責任者を宛先にします。
役名とフルネームを、自分の名前より上方もしくは前方に記載します。敬称は「殿」か「様」を使用するのが一般的です。
宛名は書類の受取人を示すため、正確な役職名と氏名を確認して記載しましょう。
退職届・退職願は、手書きとパソコンでの作成どちらがいい?
退職願は手書きかパソコンどちらで作成しても問題なく、法律上でも規定はありません。
ただし、会社によっては手書きを義務付けている場合や、退職願のフォーマットをあらかじめ用意している企業もあります。勤務先に確認しましょう。
退職届・退職願を書く前に準備したいこと
退職届や退職願を作成する前に、必要な文房具や資料を準備しておくと、スムーズに書類作成が進みます。以下のポイントをチェックしましょう。
- 【手書き】紙や封筒、筆記用具を用意する
- 【PC】テンプレートをダウンロードする
準備をすると、丁寧な印象の退職届・退職願を作成できます。
【手書き】紙や封筒、筆記用具を用意する
手書きで退職届・退職願を作成する場合は、以下の文房具を揃えましょう。
- 便箋
- 封筒
- 筆記用具
便箋は白色のもの(罫線があってもなくても構わない)を選びます。サイズはB5が標準的ですが、A4も使用可能です。見た目の統一感や印象を考え、公的な文書にふさわしい無地のものが望ましいでしょう。
封筒も白色の無地を用意すると良いでしょう。ビジネス文書としての正式感を保つため、カラフルなものや模様入りは避けるべきです。
筆記用具は黒のボールペンか万年筆を使用します。摩擦で消えるタイプのボールペンは、時間経過により文字が消える恐れがあります。会社から再提出を求められる可能性もあるため、消えないタイプのペンを選びましょう。
【PC】テンプレートをダウンロードする
パソコンで退職届・退職願を作成する場合、インターネット上にはさまざまなテンプレートが用意されています。
テンプレートをダウンロードして活用すれば、書式や文言に悩まずに書類を簡単に作成できます。WordやExcelなどの一般的な形式で提供されている場合が多く、自分の状況に合わせて内容を編集可能です。
テンプレートを利用すれば、見栄え良く整った文書を作成できるだけでなく、必要な項目の抜け漏れも防げます。
以下で退職届と退職願のテンプレートをダウンロードできるため、ぜひ利用してみてください。
退職届のテンプレートはこちら
退職願のテンプレートはこちら
退職届・退職願の封筒を準備する際のポイント
退職届・退職願を封筒に入れて提出する場合、正式な作法があります。以下のポイントを押さえて、失礼のない形で準備しましょう。
| 項目 | ポイント |
| 便箋の折り方 | ・向かって上部が上に重なるよう三つ折りにする ・文字が書いてある面を内側に折る |
| 封筒への入れ方 | ・便箋が上の右端の上部にくるように入れる ・封をする場合はのりで閉じ、封の折り返し部分に「〆」の字を記載 |
| 封筒の色とサイズ | ・白無地で郵便番号枠なしの封筒を使用 ・用紙がA4なら長形3号、B5なら長形4号を選ぶ |
| 表面の記載内容 | ・中央やや上寄りに「退職願」または「退職届」と縦書きで記載 |
| 裏面の記載内容 | ・左下に所属部署(正式名称)とフルネームを記載 |
| 筆記具 | ・黒ボールペンまたは万年筆を使用 ・サインペンや筆ペンはNG |
| その他注意点 | ・手渡しの場合は封を閉じなくても良い ・茶封筒や郵便番号枠ありの封筒は避ける ・中身が透けない二重封筒を選ぶと良い |
上記の項目を守り、提出しましょう。
退職届・退職願の提出の流れや渡し方
退職を円滑に進めるために、適切な手順で退職届・退職願を提出してください。
- 退職の意思を固める
- 直属の上司に退職を申し出る
- 退職届を提出する
- 退職する
まず退職の意思を固めてから伝えましょう。一般的には、退職を希望する日の1~2カ月前までに申し出ることを規定している会社が多い傾向です。
退職希望日を記載した退職願を作成し、直属の上司に退職を申し出て、退職願を直接手渡します。退職の承認を得たら、正式な退職日を決定します。
退職日が確定したら、退職届を提出しましょう。会社規定の退職届が必要な場合もあるため、上司に確認してから準備するのが無難です。決められた手続きを済ませて退職します。
退職願・退職届を出すタイミングと出し方は、就業規則や社内規定で確認しましょう。メールや郵送などの指定がなければ、会議室などほかの社員がいない場所で直属の上司に直接手渡すのがマナーです。
退職届・退職願に関するQ&A
退職届・退職願に関連して、よくある疑問や悩みについて回答します。
- 退職届・退職願を受け取ってもらえない場合は?
- 一度提出した退職届・退職願は撤回できる?
- アルバイト・パートも退職届が必要?
- 突然辞める場合の書き方は?
疑問を解決し、スムーズな退職手続きを進める知識を身につけましょう。
退職届・退職願を受け取ってもらえない場合は?
退職届・退職願を受け取ってもらえない場合でも、法的には退職する権利は保障されています。
民法627条1項では「退職日の2週間以上前に退職の意思表示をすること」と定められています。そのため、2週間以上前に退職を意思表示していれば、退職届の受理とは関係なく退職可能です。
上司に受け取ってもらえないときは、人事部長などの責任者にメールや内容証明郵便で送るなどの対応をとりましょう。法的には意思表示が相手に届いた時点で有効となるため、証拠を残した意思表示が大切です。
参考:民法|e-GOV
一度提出した退職届・退職願は撤回できる?
退職届は原則として撤回できませんが、退職願は会社側が承諾する前であれば取り下げることが可能です。
退職届は自主退職の意思表示を意味しており、相手に届いた後は原則撤回できません。一方、退職願の場合は会社が承諾すれば取りやめることが可能です。
したがって、撤回を希望する場合は、できるだけ早く申し出てください。時間が経過するほど人事異動や後任採用など会社側の対応が進み、撤回が難しくなる可能性が高まります。
アルバイト・パートも退職届が必要?
パートやアルバイトは基本的に口頭で退職の意思を伝えるだけで問題ありません。
ただし、会社側が退職を認めない場合や、トラブルを避けたい場合は退職届を提出すると安心です。書面で意思表示しておくと、後々「言った言わない」のトラブルを防止できます。
また、長期間勤務していた場合や重要な役割を担っていた場合など、状況によっては書面での退職届を求められる場合もあります。職場の慣習に合わせて対応してください。
突然辞める場合の書き方は?
突然辞める場合でも、退職届・退職願の基本的な書き方は変わりません。
急な退職であっても、退職理由を簡潔に言葉で説明し、引継ぎや残務処理への協力姿勢を示しましょう。たとえば「一身上の都合により、誠に勝手ながら○月○日付けで退職いたしたく存じます」などの形で退職の意向を伝えます。
急な退職で迷惑をかけることへの謝罪や、できる限りの引継ぎに協力する旨は口頭で伝えると良いでしょう。
退職届の例文を知って、円満な退職につなげよう
退職届や退職願は会社に退職の意思を正式に伝える重要な書類です。タイトル、退職理由、退職日、宛名などの基本的な記載事項を押さえ、会社の就業規則に沿って提出しましょう。
退職の悩みや今後のキャリアについて相談したい方は、キャリア相談プラットフォームのcoachee(コーチー)の利用がおすすめです。
経験豊富なキャリアコーチが、あなたの退職に関する不安や今後のキャリアプランについて客観的なアドバイスを提供します。
退職後の進路に迷いがある場合も、専門家の視点から最適な選択肢を見つけるサポートが受けられます。1回1,000円から気軽に相談できるので、退職を考えている方は一度利用してみてはいかがでしょうか。


