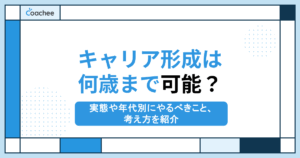キャリア形成は何歳まで可能?実態や年代別にやるべきこと、考え方を紹介
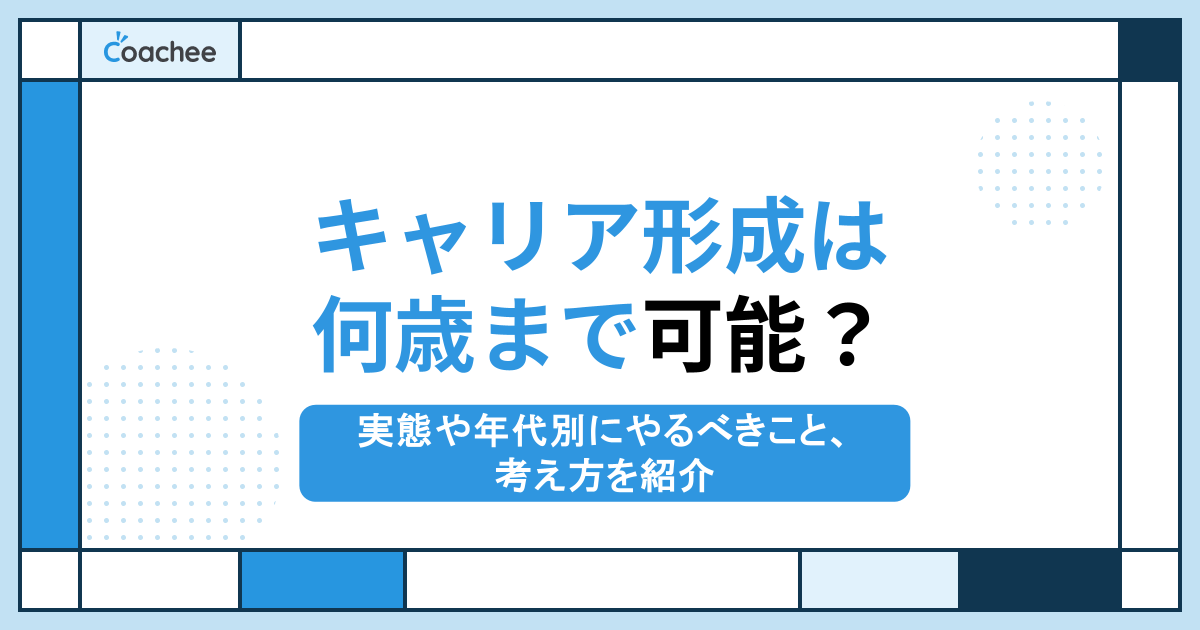
「今の年齢でもキャリア形成は可能なのかな?」
「年齢を重ねるとキャリアアップが難しくなり、転職が難しくなる?」
年齢を重ねるにつれて、キャリア形成に対する不安や疑問を抱く方は多いでしょう。
本記事では、キャリア形成の年齢的な現実から、年齢別のやるべきこと、年齢を重ねてもキャリアを築く方法まで詳しく解説します。法的な年齢制限の実態や、不安を解消する考え方も紹介するため、すべての年代の方に役立つ内容です。
年齢に関係なく充実したキャリアを築くヒントを見つけましょう。
「年齢の壁を感じてキャリアに悩んでいる」という方には、キャリア相談プラットフォーム「coachee」がおすすめです。経験豊富なキャリアコーチが年代に応じた最適なキャリア戦略を提案し、あなたの可能性を最大化するサポートを行います。
1回1,000円から気軽に相談できるため、以下のリンクからまずはサービス詳細をご確認ください。
キャリア形成は何歳まで可能?実態を解説

キャリア形成に「何歳まで」という明確な線引きは存在しません。ただし、転職市場の傾向や法的な仕組み、そして社会全体のキャリア観の変化を考えると、年齢との関係を理解しておくことは大切です。
本章ではキャリア形成が何歳まで可能なのかを解説します。
転職市場では年齢による影響がある(若い年代が有利)
結論、転職市場では若い世代の方が採用されやすい傾向があります。企業はポテンシャルや将来性を重視するためです。
例えば、Job総研の「2022年 転職年齢に関する意識調査」では、全体の7割以上が「転職に年齢の上限がある」と回答しており、平均は41.4歳、最も多かった回答は35歳でした。年代別にみると、20代の約8割、30代の約7割、40代では7割超、そして50代では9割以上が「年齢の壁を感じる」と答えています。
さらに、dodaの「転職成功者の年齢調査(2024年版)」では、転職成功者の約36.7%が25〜29歳、23.1%が30〜34歳と、若い世代の割合が多いことがわかります。
とはいえ、40代以降でもキャリア形成が不可能というわけではありません。むしろ経験やスキルを活かすことで、新しい道を切り開いている事例も多く見られます。
出典:
転職成功者の平均年齢調査【最新版】年代別の転職活動のポイントは?|doda
2022年 転職年齢に関する意識調査|Job総研
法的には年齢制限は原則禁止されている
法律上は「年齢を理由に採用制限を設けること」は原則として禁止されています。これは労働施策総合推進法で定められており、事業主は求人募集の際に年齢による差別を行ってはいけないとされています。
ただし、例外も存在します。例えば「長期的にキャリア形成を行う必要がある若手を募集する場合」や「特定の資格を持つ40歳未満の人材を求める場合」などは認められています。求人票で「35歳未満(職務経験不問)」や「40歳未満(簿記2級以上)」といった表記を見かけるのは、この例外規定に基づいているのです。
つまり、法律上は年齢による排除を防ぐ仕組みが整えられている一方、採用現場では条件付きで年齢制限が設けられるケースもあります。
参考:
厚生労働省「募集・採用における年齢制限禁止について」
厚生労働省「例外事由に該当する具体例 ②」
生涯学習時代でキャリア形成の考え方が変化している
従来は「若いうちに専門分野を選び、一つの道を突き進む」ことが理想的なキャリアとされていました。しかし現代では、その考え方が大きく変わりつつあります。
社会全体で生涯学習が重視されるようになり、年齢に関係なく学び直しや新しい挑戦をする人が増えています。30・40代から異業種に転職したり、副業を始めて複数のキャリアを並行して築いたりする動きも珍しくありません。
このように、キャリア形成は「一度決めたら変えられないもの」ではなく「自分の成長や興味に合わせて柔軟に選び直せるもの」へとシフトしています。
【年齢別】キャリア形成の実態とやるべきこと
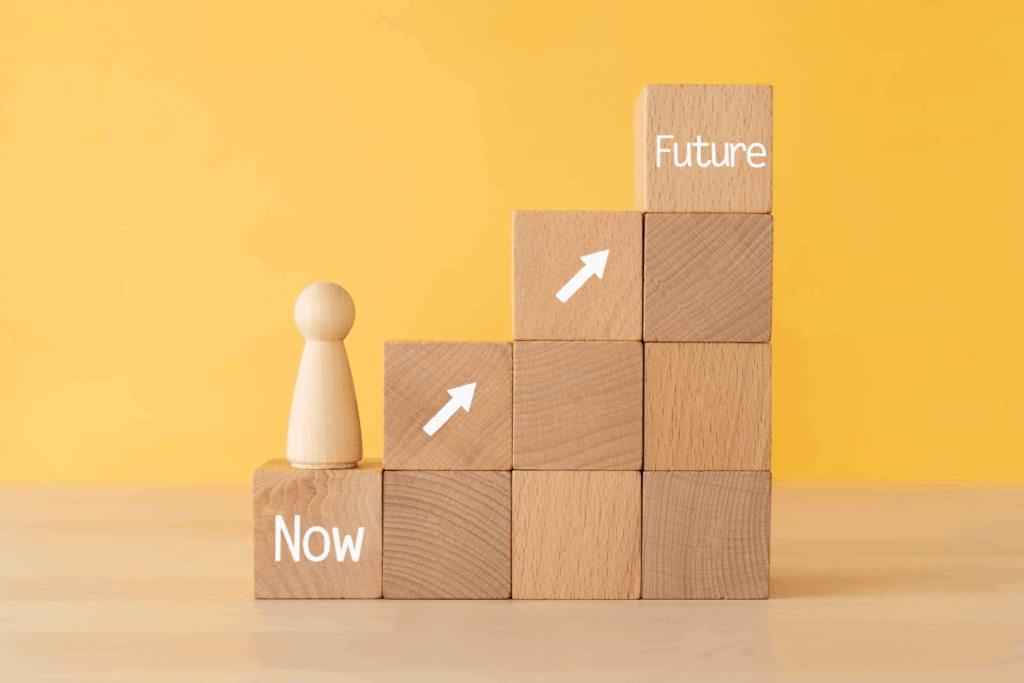
キャリア形成は年代ごとに直面する課題や求められる行動が異なります。
| 年代 | キャリア形成に関する実態 | やるべきこと |
| 20代 | ・異業種への転職割合は50%超、異職種への転職割合も40%超 ・約9割が新たなスキル習得が必要と感じている ・成長実感を得ている20代は約3割のみ、43.3%は実感を得られていない | ①基礎スキルを習得する:業界知識・専門技術・ITスキルを磨く ②経験の幅を広げる:インターン参加、新規プロジェクトや難題に挑戦 ③視野を拡大する:異分野に触れ、多様な経験を積む |
| 30代 | ・管理職転職者の21.8%が30代 ・ワークライフバランスが重視され、特に女性は勤務地や通勤時間を重視した転職が増加 ・約8割が自律的・主体的キャリア形成を希望する | ①マネジメント力を高める:リーダーとして部下を指導 ②専門性を高める:自分の強みを明確にして磨く ③家庭と仕事の両立:長期的な働き方・生活設計を見直す |
| 40代 | ・40歳時点で転職経験者は62.6%に達し、転職意向がある人も60.6%と高水準・40代は学習 ・自己啓発の取り組みが全体平均を下回り「時間が取れない」(43.6%)「費用負担が大きい」(31.5%)が主な障壁 | ①経営視点強化:部署や事業全体を俯瞰して意思決定 ②ビジネス知識の拡大:財務・戦略・マーケティングを学ぶ ③新分野挑戦:リスキリング制度で新スキルを習得 |
| 50代以降 | ・転職入職率は3.5%と低水準・転職で年収が上がったのは全体の2~3割 ・定年後のキャリア準備が不十分と感じるミドルシニアが多数 | ①長期キャリア設計:65歳以降も見据えたライフプラン策定 ②継続学習:デジタル基礎スキルをアップデート ③後進育成:メンターとして若手を指導 |
年代ごとに直面する現実は異なりますが、どの世代でも「学び続ける姿勢」と「環境の変化に適応する柔軟性」が欠かせません。自身の強みと課題を把握し、時期に応じたキャリア形成に取り組むことが将来の安定につながります。
キャリア形成の具体例については、以下の記事で解説しているので、ぜひご覧ください。
【年代別】キャリア形成の具体例とは?必要な5つのスキルや考え方を解説
出典:
職業人生の長期化・多様な働き方が広がる中での人材開発・キャリア形成|厚生労働省
20代対象アンケート|PRTIMES
管理職への転職に関する調査|Indeed
若手・中堅社員の自律的・主体的なキャリア形成に関する意識調査|株式会社リクルートマネジメントソリューションズ
40歳のキャリア実態と『なりたい自分』意識調査2025 vol.1|PRTIMES
学び直しの実態調査|トライズ株式会社
【2025年最新】年代別の「転職率」と「転職理由」とは? 20代・30代・40代・50代それぞれ解説|マイナビ キャリアリサーチLab
年齢を重ねてもキャリア形成を続ける2つの方法
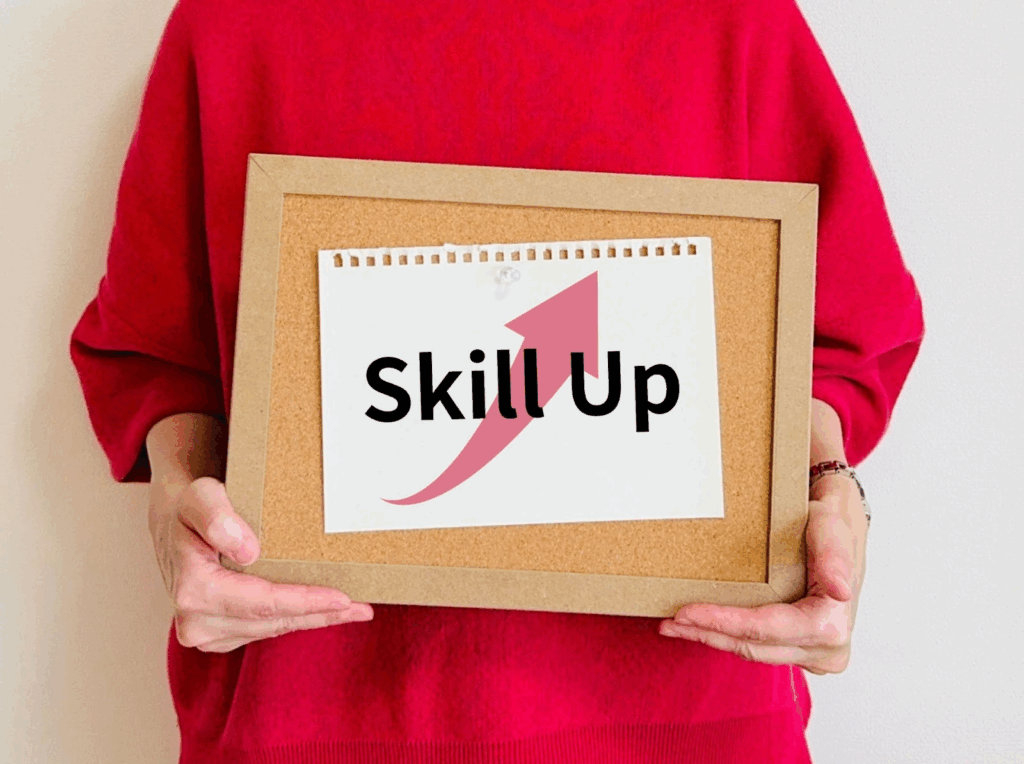
年齢を重ねてもキャリア形成を止める必要はありません。むしろ経験を積んだからこそ取り組める方法があります。ここでは、年齢を重ねてもキャリア形成を続ける2つの方法を紹介します。
1.専門スキルを磨いて市場価値を高める
どこでも通用する形で専門スキルを磨き続けることが、市場価値の向上につながります。例えば、営業職でも、提案資料の作成力や顧客分析の経験を深めることで、企画職やマーケティング職への展開が可能になります。
市場価値は「能力と経験の掛け合わせ」で決まるうえ、時代や技術の進化によって変化し続けます。現在のスキルが5年後に通用しない可能性もあるため、自分の経験を定期的に見直し、再現性を意識してアップデートし続けてください。
2.学び直しで新しいキャリアを築く
学び直し(リスキリング)は、第二のキャリアを築くための有効な手段です。パーソル総合研究所の調査では、学び直しに取り組んだ人の6割以上が「仕事の成果が高まった」と回答し、7割近くが「学びが将来のキャリアに役立つ」と感じています。
さらに、学び直しを通じて年収が増えるケースも確認されています。正社員の場合は平均で年間12万円、3年以上続けた人では年間30万円の収入増が見込まれるという結果もあります。
新しい分野を学ぶことで視野が広がり、今までの経験と組み合わせて新しいキャリアの選択肢を作り出せるでしょう。
出典:ミドル・シニアの学びと職業生活に関する定量調査|パーソル総合研究所
キャリア形成における年齢の不安を解消する考え方

年齢を重ねると「もう手遅れではないか」「若い人の方が有利だ」と不安を感じやすくなります。しかし、実際には年齢そのものが壁になるわけではありません。大切なのは、キャリアをどう捉え、どう行動するかという考え方です。
以下の表では、不安を解消するための考え方と、実践ポイントを整理しました。
| 考え方 | 解説 | 実践のポイント |
| 「手遅れ」という思い込みを捨てる | 「年齢を重ねているから無理」という固定観念がキャリアの可能性を狭める。実際には、転職・学び直し・スキル習得は何歳からでも可能。 | ・成功事例を調べて「年齢を重ねても大丈夫」と理解する ・小さな挑戦から始めて自信を積み上げる・毎月1つは新しい知識・スキルを学ぶ・習慣的に読書・セミナー・資格取得に挑戦する |
| 年齢を強みに変える発想を持つ | 年齢は「弱み」ではなく「経験値の証」。若手にない視点・人脈・信頼性は年齢を重ねるほど高まる。 | ・自分の経験を棚卸しして言語化 ・面接や職場で「年齢を重ねているからこそできること」をアピール |
年齢にとらわれず、新しい学びや挑戦を続ける人ほどキャリアの可能性を広げています。不安を解消するためには、年齢を短所と捉えるのではなく、経験や成長意欲を強みとして活かす意識が欠かせません。
キャリア形成と年齢に関するよくある質問

ここではキャリア形成を考える際のよくある質問の多い2点を取り上げ、回答を紹介します。
正社員になれるのは何歳まで?
結論、正社員になるチャンスは年齢に応じて存在しますが、条件や状況によって変わります。
厚生労働省は、学校を卒業してから3年以内の既卒者については「新卒枠」での応募を認めるよう企業に促しています。したがって、既卒から正社員を目指すなら、卒業後3年以内に応募するのが有利です。
一方で、結婚や出産などでブランクがある場合は、5年以内であれば正社員登用の可能性が高いといえます。加えて、介護や運送、販売などの分野は慢性的な人材不足が続いており、年齢に関係なく正社員採用の門戸が開かれています。
未経験業界・業種への転職・キャリアチェンジは何歳まで可能?
未経験分野への挑戦に年齢制限はありませんが、現実には20代の方が有利です。厚生労働省の調査(令和元年)でも、正社員への転職入職率は20代前半が最も高く、年齢とともに低下する傾向が示されています。
30代以降でも転職の可能性はありますが、即戦力や専門性が求められるため、自身の経験をどう活かすかを明確に伝えることが重要です。
履歴書や面接では、これまでの経験を新しい職場でどう活かすかを具体的に伝えましょう。マネジメントや営業などのスキルが、異なる業界でも活用できると示すと効果的です。
出典:厚生労働省「転職入職者の状況」
coacheeのキャリア形成支援の事例

ここでは、実際にcoacheeを利用してキャリア形成を成功させた事例を紹介します。
ある方は事務職として働いていましたが、給与が低く、生活を維持するためには残業をせざるを得ない状況に不満を感じていました。もっと納得できる働き方を目指すために、キャリア形成の支援サービスを探す中でcoacheeに出会います。
【coacheeを選んだ理由】
他のキャリア支援サービスは数万円から数十万円と高額なものが多い中、coacheeは数千円から利用できる点が大きな魅力でした。コストを抑えながらも専門的なサポートを受けられることが、利用の決め手となりました。
【サポートの内容】
キャリア相談では「自分はどんな働き方を望んでいるのか」というキャリア観を深掘りし、価値観を言語化しました。その結果、以下のような方向性が明確になりました。
- 業務効率化に強みを持つエンジニアとして市場価値を高めたい
- 賃金やワークライフバランスなど、納得できる条件で働きたい
さらに、コーチとの対話を通じて、それまで視野に入っていなかった選択肢を見つけられたことも収穫でした。
例えば「仕事内容にこだわりはあるが、業界にはこだわりがない」という相談に対して、コーチは「業界研究よりも業態研究を重視した方がよい」とアドバイスしてくれました。結果的に複数の業態を比較しながら、自分に合った働き方を納得して選ぶことができています。
【成果】
キャリア形成の方向性を定めたうえで転職に成功し、希望していたITエンジニアとしてのキャリアをスタートできました。
納得のいく転職がしたい!事務職からITエンジニアに転職するまでの軌跡
年齢に関係なくキャリア形成を成功させたいならcoachee(コーチー)をチェック

キャリア形成は若い方が有利ですが、年齢ごとに適切な対策を行えば十分に成功させられます。
若い世代は基盤づくりに注力し、中堅層は専門性の深化、シニア層は経験を活かした新しい役割へとシフトすることが有効です。大切なのは年齢にとらわれず、自身の強みと市場の変化を見据えて行動する姿勢です。
ただし、年齢を重ねるほどキャリアの選択肢や転職の難易度に不安を抱える方も多いでしょう。そのようなときには、キャリア相談サービス「coachee(コーチー)」の利用がおすすめです。
経験豊富なコーチが年代や状況に合わせて最適な戦略を提案し、可能性を広げるサポートをしてくれます。1回1,000円から相談できるため、将来の選択に迷いを感じたら、まずは気軽に相談してみてください。