退職時にボーナスはもらえる?満額もらうポイントやスケジュールを解説
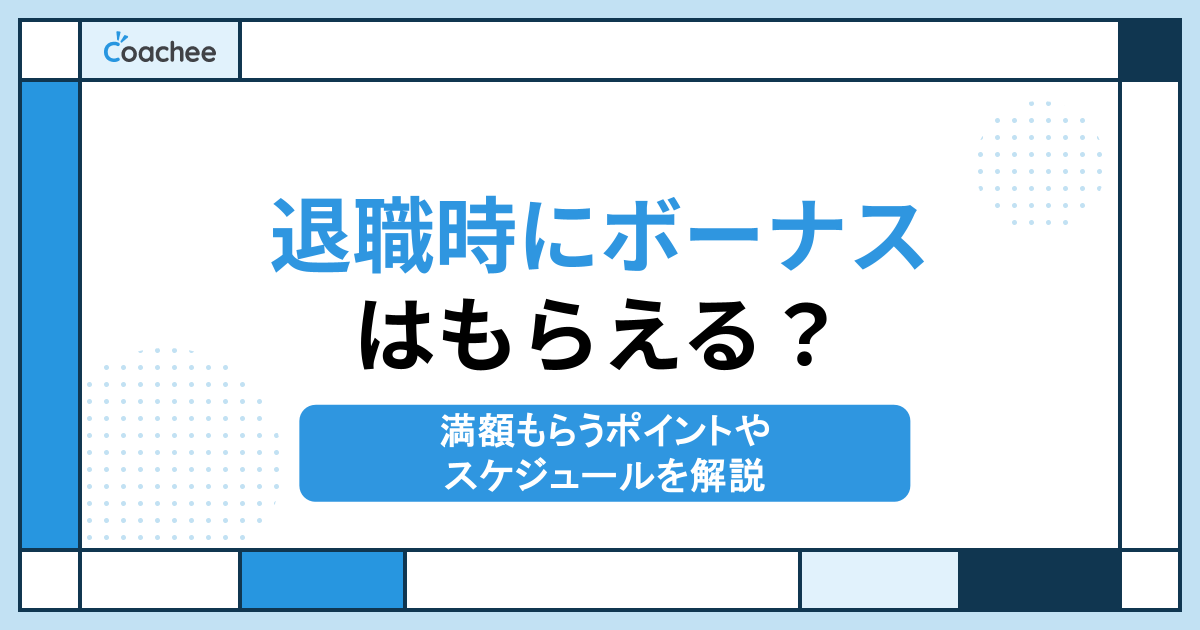
「退職するとボーナスはもらえないの?」
「ボーナス前に退職すると損をするって聞いたけど本当?」
「退職のタイミングで悩んでいる…」
退職を考える際に、ボーナスについて疑問や不安を抱えていませんか?
本記事では、退職時にもらえるかどうかやボーナス支給条件、満額もらいながら円満に退職するポイントなどを解説します。退職スケジュールや法的トラブル事例も解説しているので、退職を検討している方は参考にしてください。
本記事を読んで、納得のいく形で退職できるようになりましょう。
「退職の悩みを誰かに相談したい」という方には、キャリア相談プラットフォームのcoachee(コーチー)がおすすめです。経験豊富なキャリアコーチに相談することで、今後のキャリアプランや退職のタイミングについて客観的なアドバイスを受けられます。
以下のサイトからサービスの概要をチェックできるため、ぜひご覧ください。
そもそもボーナス(賞与)とは?給与との違いを解説
ボーナスとは、毎月の給与とは別に、業績や経営状態に応じて支払われる報酬です。給料として毎月受け取る金額とは異なり、法律で支払い義務が定められていません。そのため、計算方法や金額、支給回数などは、会社側が自由に決定できます。
給与とボーナスの違いは、支給される時期です。
ボーナスは企業ごとに支給される額や時期が異なります。一方で「給与」は、労働基準法第24条2項で「毎月1回以上の一定日に支払わなければならない」と規定されているため、毎月特定の日に一定額が会社から支払われます。
参考:労働基準法|e-GOV
退職時にボーナスはもらえる?支給条件も解説

退職者へのボーナス支給の有無は、各企業の就業規則によって異なります。
就業規則に「ボーナス支給の規定」が明記されており、支給日在籍要件が明確に定められている場合、退職日によってボーナスが支給されるかどうかが決まります。
支給日在籍要件とは、ボーナス支給日に会社に所属している社員のみを支払対象とするルールです。
支給日在籍要件から考えると、ボーナス支給日より前に退社している社員はボーナスを受け取れません。逆に言えば、支給日に会社に所属している社員には原則としてボーナスが支払われます。
【パターン別】退職時のボーナスの支給条件と金額
退職のタイミングや状況によって、ボーナスの支給条件や金額が変わります。以下では、3つのパターン別に退職時のボーナス支給について解説します。
- ボーナス支給前に退職するケース
- ボーナス支給後に退職するケース
- 有給休暇を取得するケース
それぞれの状況に応じた対応策を知っておくと、退職時のボーナス受給について状況に応じた判断ができます。
1.ボーナス支給前に退職するケース
労働契約で支給日在籍条項が設定されている場合、ボーナス支給日に在籍していない従業員への支払い義務は生じません。
たとえ前日であっても、ボーナス支給日前に退職した従業員は、支給対象にならないのが一般的です。この場合、法律上も企業側に支払い義務はありません。
ただし、支給日在籍条項が設定されていない場合や、会社都合によって解雇されたときは、支給対象に含まれる可能性があります。
2.ボーナス支給後に退職するケース
ボーナス支給後の退職では、基本的にボーナスが支給されますが、減額される可能性も考慮しましょう。
就業規則において、ボーナスの算定基準に「将来への期待値」が明示されている場合は減額される恐れがあります。企業側が「将来の貢献に対する前払い」という位置づけでボーナスを支給しているため、退職によって期待が損なわれると判断され、一部減額が認められます。
ただし、通常よりも大幅な減額の場合は請求できる場合もあります。詳しくは後述する「退職時のボーナスをめぐるトラブル事例と対処法」の「不当に減額される」を参考にしてください。
3.有給休暇を取得するケース
有給消化期間中であっても、労働契約に基づく支給要件を満たしていれば、ボーナスの支給を受けられます。法律上は雇用関係が継続していると見なされるためです。
ただし、ボーナス支給日前に退職を申し出た場合、就業規則によっては減額されたり受け取れなかったりする場合があります。例えば、就業規則に「有給休暇により会社に出社していない場合は減額する」などの記載があれば、ボーナスが減額されるケースもあるでしょう。
ボーナスを満額もらって円満に退職するための3つのポイント
本項では、ボーナスを確実に受け取りつつ円満退職を実現する3つのポイントを紹介します。
- ボーナス支給後に退職の意思を伝える
- 十分な引継ぎ期間を確保する
- 業務に支障をきたさないよう最後まで責任を持つ
ポイントを押さえると、金銭面での損失を避けながら、良好な関係を維持して退職できます。
1.ボーナス支給後に退職の意思を伝える
ボーナスを受け取ってから辞めたい場合は、ボーナス支給後に退職の意思を伝えましょう。先述したように退職することがわかっている場合、減額される恐れがあるためです。
退職したいと考えても、支給日まで待ってから申し出てください。
また、受け取ってすぐに辞めると良い印象を持たれない可能性があるため、支給後2〜3週間以上は間隔を空けましょう。
2.十分な引継ぎ期間を確保する
辞めるときは退職日から逆算し、引き継ぎ相手の業務状況にも配慮しながら、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。
引き継ぐ業務をリストアップし、退職日を決めてスケジュールを作成するとスムーズです。また、業務マニュアルを整備し、後任者がスムーズに業務を遂行できる環境を整える必要があります。
引き継ぎ期間は2〜3か月程度を目安とし、十分な時間を確保するよう心がけましょう。特に複雑な業務や専門知識が必要な仕事ほど、余裕を持って引き継ぎ期間を設定する必要があります。
3.業務に支障をきたさないよう最後まで責任を持つ
退職が決まっても、最後まで責任感を持って業務に取り組む姿勢を示しましょう。
具体的には引き継ぎ作業を行い、後任者や同僚に迷惑をかけないよう心がけましょう。
ボーナスを受け取った後でも最後まで誠実に仕事に取り組むと、良好な人間関係を維持できるので、将来仕事で協力する場合にも役立つでしょう。
ボーナスを受け取って退職・転職するスケジュール
本項では、ボーナスを受け取って退職・転職するスケジュールを解説します。
- 夏のボーナス(6月支給)をもらってから退職するスケジュール
- 冬のボーナス(12月支給)をもらってから退職するスケジュール
退職前の企業と転職先の企業の両方からボーナスをもらえる可能性があるため、ぜひ参考にしてください。
1.夏のボーナス(6月支給)をもらってから退職するスケジュール
夏のボーナス(6月支給)をもらい退職する際は、5月に転職活動を開始し、内定獲得を目指すのが理想的です。
6月に現職のボーナスを受け取り、その後退職届を提出します。7月は引き継ぎ期間として活用し、退職手続きを完了させます。8月には転職先へ入社する流れです。
この場合、8月から10月までが次のボーナス算定期間となるため、12月には転職先でのボーナスを受け取れる可能性もあります。
ただし、会社によっては入社後すぐのボーナスが支給対象にならない場合もあるため、事前に確認しましょう。
2.冬のボーナス(12月支給)をもらってから退職するスケジュール
冬のボーナス(12月支給)をもらってから辞める場合、11月に転職活動を始め、内定を獲得します。12月に現職の冬のボーナスを受け取った後、退職届を提出します。
1月は引き継ぎ期間として活用し、退職手続きを進めましょう。そして2月に転職先へ入社するパターンです。
この場合、2月から5月がボーナス算定期間となり、6月には転職先での初めてのボーナスを受け取れる可能性があります。
年度初めからの入社となるため、新年度のプロジェクトや業務に最初から携われるメリットもあるでしょう。
ボーナスをもらう前でも辞めた方いい場合
ボーナスの受給を待つことが最善の選択とは限りません。以下のような状況では、ボーナス支給を待たずに退職を検討しましょう。
- 心身の健康状態が悪化している
- ボーナスの金額が低い
経済的な利益よりも優先すべき事情もあるため、判断基準をあらかじめ理解しておきましょう。
1.心身の健康状態が悪化している
職場でのストレスが慢性化している場合、退職が遅れるほど体調不良や精神疾患のリスクが高まります。
ボーナスをもらうことで金銭的メリットは得られるかもしれませんが、心理的・身体的健康が損なわれるリスクもあります。
特に、長時間労働の継続やハラスメントによって精神的に消耗している状況では、ボーナスの支給を待たず、退職を優先すべきでしょう。健康を損なってしまうと、得られたボーナス以上の治療費や回復期間が必要になる場合もあります。
2.ボーナスの金額が低い
ボーナス支給日でも、受け取れる見込みが低かったり金額が少なかったりする場合は、気にせず退職するのも選択肢の一つです。
時間は有限であるため、転職希望先や挑戦したい業種がある場合、できるだけ早く行動に移す方が長期的には有利になるケースが多いでしょう。特に好条件のオファーがある場合、ボーナスを待つことで失うチャンスと比較検討する必要があります。
ただし、転職を急いでいなければ、ボーナスを受け取ってから退職するのも良いでしょう。メリット・デメリットを検討したうえで退職日を決めてください。
退職時のボーナスをめぐるトラブル事例と対処法
退職時には、ボーナスに関するトラブルが発生するケースがあります。本項では、よくあるトラブル事例と対処法について解説します。
- ボーナスが支払われない
- 不当に減額される
以下の項で詳しく解説します。
1.ボーナスが支払われない
支給条件を満たしているにも関わらず、ボーナスが支払われないケースがあります。
不払いの額が明確でない場合は、規定に基づき、請求金額をできる限り明確にしましょう。過去の支給実績や給与明細などを根拠とするのが有効です。
その後、口頭または電話で直接交渉します。応じない場合には、請求した事実を残すために文書でも請求しましょう。
2.不当に減額される
退職予定者のボーナスが大幅に減額されるケースもあります。
例えば、ベネッセコーポレーション事件判決(東京地判平8.6.28)では、約8割もの減額は不当と判断され、2割程度までの減額なら妥当とされました。減額理由が明確でなかったり、不当に大幅な減額がされたりした場合は違法となる可能性が高いです。
その際は、就業規則を確認し、不当な減額と思われる場合は弁護士などに相談しましょう。
参考:周知されていない就業規則を理由とする賞与の不支給|厚生労働省
退職時のボーナスに関するQ&A
本項では、退職時のボーナスについてのQ&Aを紹介します。
- 会社都合での退職でもボーナスはもらえない?
- 退職するとボーナスは返還する必要がある?
- ボーナス以外に退職時に注意したいことは?
気になる箇所を押さえておきましょう。
会社都合での退職でもボーナスはもらえない?
リストラなどの一般的な会社都合退職の場合、就業規則によっては支給される可能性もあります。
一方、懲戒解雇も会社都合とされますが、基本的にボーナスは支給されません。懲戒解雇は会社に損害を与えたなどの理由によるため、ボーナス支給条件を満たさない場合が多いからです。
会社都合退職の場合、退職金や失業給付などの面で自己都合退職より有利になるケースが多いため、退職理由を確認し書面で残しておきましょう。
退職するとボーナスは返還する必要がある?
一度支給されたボーナスを返還する義務はありません。
ボーナスは労働基準法上「賃金」と見なされるため、返還請求は違法となる場合が多いです。労働の対価として支払われた賃金を返還させることは、法律で禁止されています。
ただし、就業規則や契約書で特別な返還義務が明記されている場合のみ例外となるケースもあります。何らかの返還請求を受けた場合は、根拠を確認し、必要に応じて労働基準監督署や弁護士に相談しましょう。
ボーナス以外に退職時に注意したいことは?
退職する際は、ボーナス以外にも下記の点に注意が必要です。
- 退職金
- 未消化有給休暇
- 社会保険手続き
退職金については、就業規則や労働契約書で条件を確認し、不足分や未払いがないかチェックしてください。有給休暇をすべて取得できない際は、未消化分の有給休暇の買取ができるか相談しましょう。通常は認められていませんが、退職時の有給休暇買取ができるケースがあります。
また、社会保険手続きも重要です。退職後の健康保険や年金手続きを早めに行い、保険料負担を把握しておく必要があります。特に国民健康保険への切り替えは退職後14日以内に行う必要があるため、計画的に進めましょう。
退職も見据えたキャリアプランの相談ならcoachee(コーチー)
退職時にボーナスがもらえるかどうかは、企業の就業規則によって異なります。支給日に在籍している従業員にのみボーナスを支給するルールが設定されている場合、支給日より前に退職すると受給できないケースが一般的です。
ボーナスをもらいながらも円満に退職するためには、支給後に退職意思を伝え、引継ぎ期間を確保しながら責任を持って業務に取り組みましょう。
退職や転職に関するキャリア相談は、専門プラットフォーム「coachee(コーチー)」がおすすめです。coacheeでは、さまざまな業界に精通したキャリアコーチが、退職のタイミングや転職先の選び方など、あなたの状況に合わせたアドバイスを提供します。
ボーナスと退職時期の兼ね合いや、次のキャリアについて悩んでいる方は、1回1,000円から気軽に相談できるcoacheeを活用してみてください。


